探究する力が、
未来をひらく


自由ケ丘高校は、総合的な学習(探究)の時間に力をいれており、2025年度は「理数探究実践グループ」を立ち上げました。本グループでは、北九州市立大学の辻井洋行教授との連携のもと、約月1回のペースで探究プロジェクトを実施してきました。
ビオトープを中心とした事例をテーマに、建築デザインの観点から講義をいただきました。身近な建築物を事例に建築デザインの効果や影響を知り、探究への関心がさらに深まりました。また機械システム工学の領域においては貴重な講義動画を作成いただき、普段知ることのできない専門的な知見を得ることができました。
このページでは、生徒たちがどのようにして「問いを立て」「チームで考え」「実社会とつながるアウトプット」へとつなげていったのか?その学びの軌跡を紹介します。
まず辻井先生とともにプロジェクトリーダーを務める本学の安武先生より探究活動の目的と今後の流れについて全体的な説明があった後、北九州市立大学 国際環境工学部の辻井先生ならびに上江洲先生の特別講義を受講しました。
辻井先生からは、現在の大学や社会で求められる人材像について、「自ら課題を発見し、解決策を考える力が重視されている」というお話を頂きました。
また、そうした人材を育成する大学の活動の一例として、上江洲先生がシャボン玉石けん株式会社との産学連携で開発した「泥炭林野火災用石けん消火剤」についてのお話を伺い、研究分野を通じて学内の人々や社会と協力していく道筋についての事例を学びました。

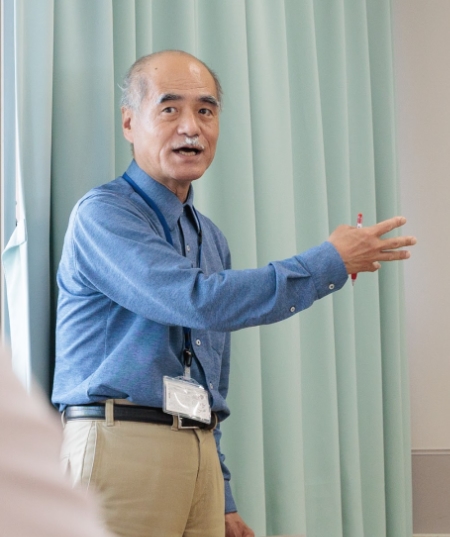
前回の授業を踏まえて、今回は建築デザイン学科の安藤真太朗教授、および機械システム工学科の宮國健司准教授の特別講義を受講しました。
大学近くのビオトープを一例として、市民にも広く開かれている研究用の構造物が、市民にあまり利用されていない理由について建築デザインおよび機械システム工学の観点から分析し、改善点を検討しました。
建築物を継続的に公共利用していくにあたっては、人間の動線を意識したデザインとそれを補助するシステムが必要であることをお話しいただきました。


生徒一人ひとりが身近な社会や学校の中から気になっている問題・小さな違和感を探し、それらを具体的に掘り下げて、探究に値するテーマにするまでの過程を体験しました。
日常生活や目にしたニュース等の中で「不便だと思っていること」や「違和感を感じていること」を付箋に書き出し、グループの中で「なぜこの話題に興味を持ったか」について発表しながら、自分の考えを言語化。探究テーマとしてブラッシュアップしました。
ここでは教員はあくまで問いのガイド役に徹し、生徒の発言を否定することなく独自の考えを深めるサポートを行いました。


Day3で発見した課題をどうすれば解決できるか、Day4では専門家である北九州市立大学の教授や大学院生を招き、似たテーマのグループ群で意見交換をしながらアイデアを深めました。
また、後半にはワークシートを活用し、課題定義及び課題解決に向けたプロセス等を整理して仮説としました。
この段階では理論的な整合性よりもアイデアを出す楽しさを重視し、教員は各班を回りながら生徒の自由な発想を促す質問で生徒の思考をサポートしました。




